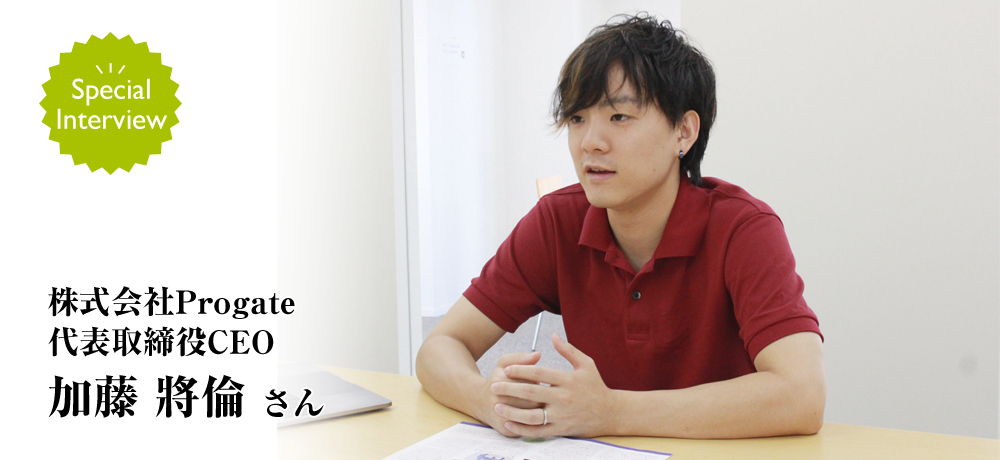かとう まさのり▶1993年生まれ。愛知県出身。小学校と中学校をオーストラリアで過ごした後、帰国。東京大学工学部電子情報工学科へ進学するも、より実践的なプログラミングを学ぶため、プログラミングサークルでの活動や受託を通じてスキルを磨く。2014年7月、大学4年生のときに株式会社Progateを創業。現在はアメリカやインドへもサービスを展開している。
どうやって作って、どう使われるかが分かるとプログラミングは楽しい!
安全に対する強い意識と最高のサービスを
―学生のときに起業されたそうですね
2014年、大学4年生のときに起業して、現在はProgateというプログラミング学習サービスを提供しています。このサービスはプログラミングを学びはじめようとする人に直感的でわかりやすく、手軽に学んでもらえるようにしたい、という思いから、徹底的にプログラミング学習のハードルを下げているのが特徴です。自分がプログラミングを学ぶのに苦労したので、初心者だった自分に教えるとしたらどうやって教えるか、ということをイメージして作りました。
―プログラミングを学ぶ上でどんな苦労があったのでしょうか
僕がプログラミングを学びはじめたのは大学3年生の頃でした。専攻を決めるタイミングで、当時は「iPhone」が普及しはじめたり「ソーシャル・ネットワーク*」(*Facebook創業者 マーク・ザッカーバーグらを描いた映画)が流行ったりしていて、自分の作ったサイトやアプリが色んな人に使ってもらえるなんて面白そうだ、と思って情報系に進んだのがきっかけでした。
しかし、大学の授業では実際にアプリをどう作るかみたいなことは教えてもらえず、プログラミングがどう発展してきたかといったアカデミックな内容のもの。しかも、授業ではWebサービスにはなじまない「C言語」を教えていました。さらに、周りの学生は子どもの頃からプログラミングをやっているような人たちも大勢いて、だんだんとついていけなくなっていきました。
何の役に立つかわからないしメチャクチャ難しいしで「プログラミング全然おもしろくないなー」と感じ、大学ではなく独学でプログラミングを勉強しようと思いたちましたが、なかなか上達しない。そこで知り合いのエンジニアの方に教えを請うようになりました。
―プログラミングが「面白い」と感じたのはいつですか?
エンジニアの方に教えてもらいながら、何かカタチにしたいという気持ちがあったので、受託の仕事をやって初めて1つサービスを作ったのですが、その経験が大きかったですね。実際に使われるサービスを作ることで、プログラミングとは何か、ということを理解して面白く感じました。
それから周りの人にもプログラミングを教えていくようになりましたが、そのときにもツールはあまり発達していなくて、教科書となる本を買ったり海外のサイトを参照したりというやり方を他の人にも勧めていました。そんなときに「自分たちでプログラミングを教える仕組みを作ればいいんじゃないか」ということに思い至り、現在のProgateというサービスを考えはじめました。
―大学でプログラミングを始める以前にはIT業界に興味はありましたか?
特別意識したことはありませんが、周りの環境の影響はあったと思います。
僕は中学生の頃までオーストラリアで育ちました。オーストラリアはIT教育の盛んな国で、普段からパソコンを使った授業を行っていたし、レポートもパソコンで書いて提出していました。それから、母がオーストラリアでエンジニアとして仕事をしていたので、プログラミングは結構身近な存在だったかもしれません。
―高校生時代はどうでしたか?
高校からは日本に帰ってきました。オーストラリア人の中では当時、日本のITは進んでいるという認識が強かったのですが、実際に帰ってきてみるとイメージとのギャップがありました。校舎も古いし課題は手書きでしていて、日本のIT教育は遅れているのかも、と思いました。
―現在の日本のIT教育に関してはどう感じていますか?
まだまだこれから、といったところだと思います。先日インドへ行った際、現地のIT教育について伺ったのですが、インドでは小学校1年生からプログラミング教育が始まります。中学生の頃にはHTMLで簡単なWebサイトが作れるようになり、高校生ではC++やJavaなどを使ったプログラミングができるようになります。そして大学に進む頃にはコンピュータサイエンス専攻を希望する学生が大勢出てくる。そういう場所を目の当たりにすると日本の5年、10年先を行っているな、と感じます。
2020年から日本でもプログラミング教育が必修化されますが、ただプログラミングを教えるというだけでなく、楽しさも伝えていかないといけないと思います。プログラミングとはどんなもので、どんな使われ方をしているのか、そういうことがわかればそれが楽しさになってモチベーションにつながると思います。
―加藤さんにとっての楽しさ、モチベーションの源は何ですか?
例えば、TwitterやInstagramなどのサービスは、どこかのすごい大人が魔法のような力で作り出しているもので、それを与えられて使うことが当たり前、と皆さん思っているかもしれません。が、プログラミングを覚えればそれらに近い機能のものはすぐ作れるようになるんですよ。それに気づいたときのワクワク感とか、そうしたスキルを持つことで自分が価値ある人間だと思えたり、他人から価値を認めてもらえたりするところがプログラミングを学んで良かったところだと思います。
ですから、私がプログラミングを通じて感じた楽しさ、面白さを、Progateを通じてこれからも伝えていきたいです。